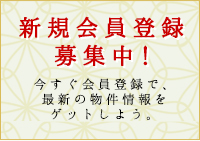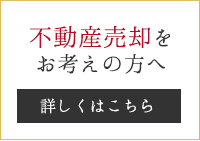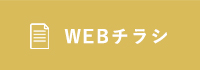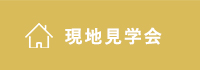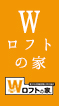命を守る火災警報器(続) ~種類と機能と注意点~【2024-11-16更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
命を守る火災警報器(続) ~種類と機能と注意点~
ページ作成日:2024-11-16

住宅用火災警報器の代表的な種類は、煙を感知して警報を出す煙式(光電式)と、熱を感知して作動する熱式(低温式)の2つです。条例で寝室・階段室などに設置が義務付けられているのは煙式。一方、熱式は熱源が近い台所や車庫向きです。さらに、電源の種類によって電池式とコンセント式がありますが、電池式の方が安価なようです。
また一般に普及しているのは、火災を感知した警報器だけが作動する単独型。しかし、寝室が多い2階建てなどの住宅向けには、ある警報器が火災を感知すると他の警報器も一斉に警報を発する連動型があります。単独型に比べてやや費用はかかりますが、その分防災性も高いので、電気店やホームセンターなどで尋ねてみてください。
ところで火災警報器は、設置すればそれで終わりではありません。年数の経過とともに、故障や電池切れによる作動不良が起こりやすくなり、万一の時に重大な結果を招くことがあるのです。これを防ぐには、年に一度は警報器の動作を確認すること。春秋の火災予防運動期間や家族の記念日など、覚えやすい時期に点検・交換をすることをおすすめします。特に、電池式の警報器は約10年ごとに電池交換が必要とされているので、機器本体や手帳・カレンダーなどに、次の電池交換時期を明記しておきたいものです。
なお、近年は火災警報器をめぐる悪質な訪問販売・通信販売が横行しているようです。警報器設置は確かに義務ですが、未設置でも罰則はありませんし、消防署が設置を強制することもありません。また、機器の価格も単体で2,000~3,000円程度で、数万円~数十万円ということはあり得ません。くれぐれもご用心ください。
月別
センチュリー21の加盟店は、全て独立・自営です。
Copyright(c)Kyotohouse Co,.Ltd. All Rights Reserved.